発達障害とは?特徴とよくある誤解
発達障害とは、生まれつき脳の働きに特性があり、行動やコミュニケーションに影響を与えるものです。決して「親の育て方」や「努力不足」が原因ではなく、個々の特性に合った対応が大切になります。
発達障害の基本的な種類
発達障害にはいくつかの種類があり、それぞれ特徴が異なります。
- 自閉スペクトラム症(ASD)
- コミュニケーションや対人関係が苦手
- 特定の物事への強いこだわりがある
- 音や光などに敏感なことが多い
- 注意欠如・多動症(ADHD)
- 集中力が続かず、忘れ物やミスが多い
- 衝動的に行動し、順番を待つのが苦手
- 落ち着きがなく、じっとしているのが難しい
- 学習障害(LD)
- 読む・書く・計算するなどの特定の学習分野が苦手
- 知的発達には問題がないが、特定の課題だけが極端に難しく感じる
- 視覚や聴覚の情報処理に困難を抱えることもある
「個性」と「発達障害」の違いとは?
子どもは一人ひとり個性が異なりますが、「発達障害」は日常生活や学校生活で困難を感じることが特徴です。
個性の範囲
- マイペースな性格
- 興味があることに没頭する
- 内向的・外向的などの性格の違い
発達障害の可能性がある特徴
- 社会生活に影響を及ぼすレベルのこだわりや苦手さ
- 学校や家庭で困りごとが続き、周囲の支援が必要になる
- いくら努力しても改善しにくい傾向がある
親が抱えがちな誤解と正しい理解
発達障害に対して、誤った認識を持ってしまうことも少なくありません。

誤解① 「しつけが悪いから落ち着きがない」
正しい理解:ADHDの子どもは、脳の特性により集中や衝動のコントロールが難しい。適切な環境を整えることが大切。
誤解② 「話せるなら自閉スペクトラム症ではない」
正しい理解:ASDの子どもでも言葉の遅れがないケースもある。ただし、会話のキャッチボールが苦手なことが多い。
誤解③ 「努力すれば普通になれる」
正しい理解:発達障害は「治す」ものではなく、特性に合わせた支援が重要。本人が生きやすい方法を見つけることが大切。
発達障害の理解を深めることで、子どもに合った適切な対応ができます。大切なのは「治す」のではなく、「特性を理解し、サポートすること」です。
気になる行動チェックリスト|発達障害の可能性があるサイン
発達障害は「行動の特性」として現れることが多く、子どもによって症状の出方は異なります。日常生活で気になる行動がある場合、発達の特性を理解することで適切な対応がしやすくなります。以下のチェックリストを参考に、子どもの行動の傾向を確認してみましょう。
コミュニケーションの違和感(会話のズレ、人との距離感など)
発達障害の中でも 自閉スペクトラム症(ASD) の傾向がある子どもは、他者との関わり方に特徴が見られることが多いです。
チェックポイント
- 会話のキャッチボールがかみ合わず、一方的に話すことが多い
- 相手の表情や気持ちを読み取るのが苦手で、適切なリアクションができない
- 興味のある話題になると、相手の反応に関係なく話し続ける
- 人との距離感が極端に近い、または離れすぎている
- 「冗談」や「比喩表現」を理解しにくく、言葉を文字通り受け取る
専門的な視点
社会性やコミュニケーション能力は、幼少期から段階的に発達するものです。しかし、ASDの特性がある場合、相手の意図をくみ取ることが難しい ため、対人関係のトラブルが増えやすくなります。親が「人と関わる楽しさ」を伝えながら、視覚的なサポート(イラストや絵カード)を活用すると、社会性の向上につながることもあります。
集中力や注意力の問題(すぐ気が散る、忘れ物が多いなど)
注意欠如・多動症(ADHD) の特性を持つ子どもは、注意力を持続させることが苦手な傾向があります。
チェックポイント
- 何かをしていても、すぐに別のものに気を取られてしまう
- 宿題や作業を始めても、途中で投げ出してしまうことが多い
- 忘れ物やなくし物が頻繁にある(筆箱・ノート・連絡帳など)
- 順番を待つのが苦手で、すぐに割り込んでしまう
- 会話の途中で話が飛び、まとまりのない話し方になる
専門的な視点
ADHDの子どもは、脳の「実行機能(物事を計画・遂行する力)」に課題があることが多いため、
- 目の前の刺激にすぐ反応してしまう
- 物事の優先順位をつけるのが苦手
- 記憶を整理して保持することが難しい
といった特徴が見られます。対策としては、「視覚的な手がかり」を使う のが効果的です。たとえば、タイマーを使って時間管理をする、やることリストを貼る、モノの定位置を決めるなどの工夫が役立ちます。
こだわりや感覚の違い(同じ行動を繰り返す、大きな音が苦手など)

発達障害の特性として、感覚の過敏さや独特のこだわり を持つことがあります。これは、ASDの子どもによく見られますが、ADHDの子どもにも一部当てはまることがあります。
チェックポイント
- いつも決まった順番で行動しないと気が済まない
- 服のタグや靴下の縫い目を「チクチクして嫌」と感じる
- 騒がしい場所(花火・掃除機・チャイムの音)が極端に苦手
- 食べ物の食感や温度に強いこだわりがあり、特定のものしか食べたがらない
- 何度も同じ動作を繰り返す(手をひらひらさせる、特定のものを並べるなど)
専門的な視点
脳の情報処理の仕方に違いがあるため、「感覚が過敏」「逆に鈍感」などの特徴が現れます。たとえば、聴覚過敏 の子どもは、他の人には気にならない音でも「痛いほど大きく聞こえる」ことがあります。逆に、痛みに鈍感で転んでも泣かない子どももいます。
これらの特性に対しては、
- 苦手な刺激を減らす工夫(イヤーマフを使う、肌触りの良い服を選ぶ)
- 行動の予測可能性を高める(スケジュールを視覚化する)
といった対応が有効です。
発達障害の可能性を感じたら?家庭でできるサポート方法
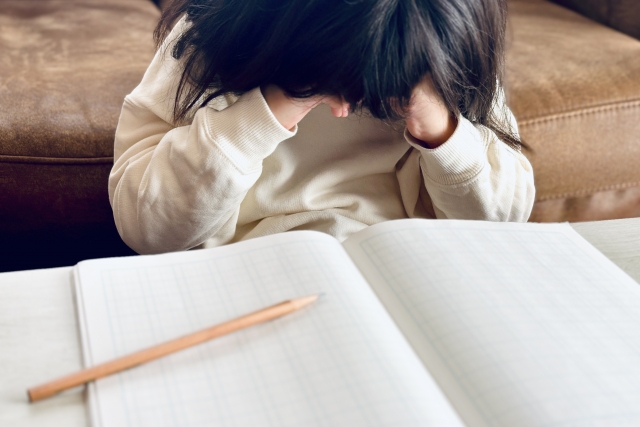
発達障害の特性を持つ子どもは、環境や関わり方を工夫することで生活しやすくなります。家庭でできるサポートのポイントを紹介します。
① 子どもの特性に合わせた接し方の工夫
子どもが理解しやすい伝え方を心がけましょう。例えば、指示をシンプルにする、視覚的なサポート(イラスト・スケジュール表)を活用することで、伝わりやすくなります。また、成功体験を積めるよう、小さな達成を褒めることも大切です。
② 環境を整えることで生活しやすくするポイント
集中力が続かない子どもには、静かで整理された空間を作る、必要なものを定位置に置くなどの工夫が役立ちます。また、感覚過敏がある場合は、騒音を避ける・肌触りの良い服を選ぶなどの配慮も有効です。
③ 「困った行動」の背景を理解し、適切に対応する
注意散漫やこだわりの強さなどの行動には、本人なりの理由があります。叱るのではなく、何が原因でその行動をしているのかを観察し、代わりの方法を教えることで、ストレスを軽減できます。
無理に変えようとせず、子どもの特性を尊重しながら、寄り添う姿勢を大切にしましょう。
専門機関への相談タイミングと受診の流れ
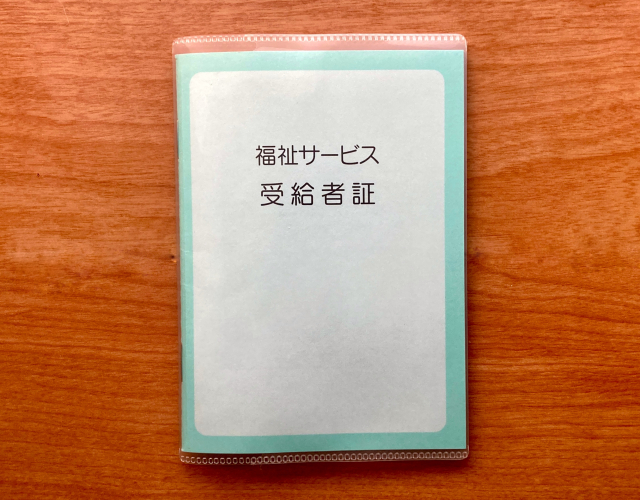
どんなときに相談すべき?発達相談の目安
「集団行動が極端に苦手」「会話がかみ合わない」「こだわりが強すぎて日常生活に支障がある」などの様子が見られる場合は、一度専門機関に相談してみましょう。早めの対応が、子どもの成長をサポートする鍵となります。
相談できる機関
発達の相談は、小児科(発達外来)・発達支援センター・児童相談所・学校の先生などが対応してくれます。地域によって支援窓口が異なるため、市町村の相談窓口を確認するのもよいでしょう。
受診までに準備しておくこと
医師や専門家に正しく伝えるために、気になる行動や困りごとをメモしておくのがおすすめです。また、幼少期からの成長の様子や、日常生活での具体的なエピソードも整理しておくと、より的確なアドバイスを受けられます。
子どもを伸ばすために大切なこと|親ができる心構え
発達障害は決して「不幸」ではなく、強みを伸ばす視点が大切です。得意なことに目を向け、それを活かせる環境を整えることで、子どもの可能性は広がります。
また、親が一人で抱え込まないために、学校・専門機関・家族などのサポートを活用しましょう。悩みを共有することで、心の負担も軽くなります。
子どもの未来を前向きに考え、特性を理解しながら温かく見守ることが、自己肯定感を育み、成長を支える大きな力になります。




コメント